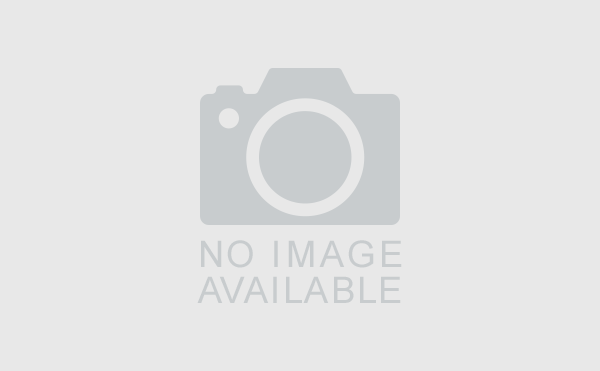国分寺と金光明経の謎
2025.3.24 三浦茂
聖武天皇は国分寺に金光明経(金光明最勝王経)を納め、国分尼寺には法華経を納めて読経させた。(尼寺でも金光明経を読経した。)国分寺を「金光明四天王護国之寺」と名付けたのは飢饉、疫病、内乱の危機に直面した聖武天皇が国の平安回復を願い「この経を崇拝すれば四天王が国難を救う」と書いてある金光明経に頼ったからとされる。
金光明経について
他の経と比べるとずいぶん遅れて4世紀ころインドで成立。内容は空の大乗思想を基調。まず経典を護持する功徳を説く。次いで本論。「懺悔」がこの経の主テーマ。仏教を含めインドの世界観では人の行為は業であり、良い業も悪い業も輪廻転生により生まれ変わった世界で報いを受ける。業と報いは絶対切り離せないもので人は輪廻を繰り返すというものである。釈迦はこれを否定し、思想的に一歩後退した大乗仏教では輪廻を前提とし、懺悔と回向によって業報の法則(因果応報)を超越できるとした。
本文の後に非常に長い付録部分があり、そこに四天王などの神々が経を護持する国王国土を守る、とする章がある。そのほかに様々な経の功徳などが書いてある。私見ながらこの部分の内容に統一性がなく、初期の段階で別の経典が付け加えられたものだろうと考える。。
西域地方に伝わった時には本文ではなく付け足されたインド土着信仰に由来する四天王崇拝が起こり、中国では金光明懺悔法が流行したという。漢訳は5世紀北涼(五胡十六国時代)の曇無讖訳の金光明経4巻、隋(589~618年)の宝貴訳の合部金光明経8巻、唐の義浄訳の金光明最勝王経10巻がある。聖徳太子が蘇我馬子とともに物部氏と争った時(587年)、四天王に勝利を祈り、戦勝後四天王寺が建てられたといわれている。時代的に日本に伝わったのは曇無讖訳の金光明経である。ところで、金光明経の「滅業障品」の部分はサンスクリット原典にも曇無讖訳にも存在しない(吉田一彦)ので後世の付加と考えられる。他の翻訳があったかもしれないが「滅業障品」の部分は中国製だろうか。中国で流行した金光明懺悔法との関係が不明である。隋の宝貴訳の合部金光明経の内容が分からない。日本に伝わったかも分からない。義浄訳の金光明最勝王経はインドで手に入れた金光明経の最新版の翻訳であり分量が多いのでこの時初めて「滅業障品」が加わった可能性がある。勅命で義浄に翻訳させた則天武后は権力維持のため偽りのお経を作らせたほどの人物ではあるが、金光明経は元々懺悔滅業による救いを説くものであったから「滅業障品」の部分が偽教の可能性は半々だろう。聖武天皇が注目した金光明最勝王経の要点は「四天王護国品」と「滅業障品」だったわけである。四天王による加護を求める国分寺建立の詔の文は金光明最勝王経の滅業障品が引用されており、文頭部分には聖武天皇の懺悔の語句が入っている。
聖徳太子以後、大化の改新で蘇我氏勢力を除いたためようやく天皇権力は安定する。それまでの個人寺院に代わって国家が寺を作り管理するようになる。蘇我氏の氏寺であった飛鳥寺も国の管理下に置かれた。百済寺(後の大官大寺、大安寺に繋がる)は初の国立寺院で、藤原京時代に川原寺、薬師寺を合わせて国の四大寺となった。壬申の乱後、天武天皇は中央集権国家を目指し、律令制を採用するとともに仏教政策を強化した。地方にも寺院建設を進め礼拝させた。日本書紀によれば、
天武9年(690)初めて金光明経を宮中および諸寺に説かせた。
天武15年(685)諸国の家ごとに仏舎を作り、仏像、経巻を安置し礼拝供養を命じた。
(注 家ごとにとあるが実際には地方豪族のことか、また仏舎を国府に付設された寺院(国府寺)を指すか。国分寺以前の豪族の寺として三河では岡崎の北野廃寺、豊川では医王寺、弥勒寺があり、国府寺とすれば国府に近い山の入り遺跡の寺などがこれに当たると思われる。個人的には国府遺跡エリア内の金堂という地名も興味深い。)
持統6年(692)京師、四畿内で金光明経を講説させた。
持統8年(694)金光明経を諸国に頒けた。
大宝3年(703)四大寺で金光明経を読ませた。
など記録がある。この段階ではまだ曇無讖訳の金光明経で、社会は比較的安定していたから罪と懺悔の意識は希薄で読経は一般的な社会安定を願ったものと思われる。続日本紀によれば聖武天皇の神亀2年(725)「僧尼をして金光明経を読ましめよ。もしこの経なくは、すなわち最勝王経を転して、国家を平安ならしめよ」とある。(疑問・これは奇妙である。普通は新しいお経がない寺院は古いものでもよい。とするのではないか?)このころ古い金光明経から新たに伝わった新訳版の金光明経最勝王経への交替が始まったと思われる。
ところがこの後、凶作、飢饉、地震に続き天平7年(735)には九州に疫病が大流行し多数の死者が出た。737年(天平9)には更に大規模な流行が起きて都にも及び政府の高官が多数死亡して政務ができない状態になった。全国で100万~150万人が死亡する大惨事になった。政府は炊き出しや税の免除など行ったが、災害には打つ手がなく神仏に鎮静を祈るしかなかった。深刻に神仏に救いを求める時代が訪れた。この時期の宗教政策と金光明経最勝王経の位置づけを見る。
続日本紀によれば、 *以下金光明最勝王経を最勝王経と略す
天平4年(732)凶作、疫病起こる。
天6(734)諸国に大地震。 得度に最勝王経と法華経の暗唱を規定(僧の条件)。
天7(735)2月に新羅使入京。3月遣唐使帰国。(疫病の原因か)
九州に疫病(天然痘)、飢饉。 神祇に祈り、諸寺に大般若経を転読さす。
玄昉、道慈に褒賞。(読経により疫病が一時鎮静のためか。)。
天8 九州で流行続く。
天9(737)天然痘が再び流行
3月、国ごとに釈迦三尊像を造らせ、大般若経を一部書写さす。
(大般若経は文字通り600巻もある大部なもので、玄奘が3年かけて漢訳した。
僧が読みあげるのに4,5日かかるという。)
4月、詔して幣を諸社に奉り祈禱らしめたまふ。賑恤。
道慈の提案で大般若経転読を国家の儀礼、恒例の行事とする。
5月、神祇を奠祭らしむれども効験を得ず。大赦実施。
宮中で大般若経を転読。
*神社に祈るが効果がなく、天皇は次第に仏教に傾倒していく。
6月、朝廷政務の停止(廃朝)。
7月、大和、伊豆、若狭、伊賀、駿河、長門で疫病と飢饉を報告。賑恤。大赦。
*前後して藤原四兄弟が死亡。
8月 2日 諸国の僧尼を沐浴させて月のうちに二、三度最勝王経を読ませ、月
の六斎日には殺生を禁断させる。
13日 諸国の田租と出挙の免除。
15日 天下太平国土安寧のため宮中で僧700人を請きて大般若経、最
勝王経を転読。
10月、宮中、大極殿で最勝王経を講す。
12月、大倭(やまと)国を改めて大養徳国とす。
*ビックリ。意味が分からない。縁起が悪いので国名まで変えたのですか?
*当初大般若経に祈祷していたものがこのころ最勝王経に力点が移る。その変化
は道慈の影響があったと考えられる。
天10(738) 諸国で最勝王経を講読。
天12(740) 国ごとに法華経10部を写させ、七重塔を建てさせる。
*国家行事に法華経が初出。
藤原広嗣の乱
天13(741) 国分寺建立の詔。初めて独立した尼寺が成立した。
国分尼寺と法華経が急に表舞台に登場したが、それ以前の経の配布、釈迦三尊の造像、七重塔の建設は結果として国分寺の準備になった。悲田院設置など弱者への取り組みをした光明皇后は多くの人民の苦しみに心を痛めたであろうし、四兄弟の死に、次は自分か、と恐怖を持っただろう。日本書紀には、敏達天皇時代、蘇我氏と物部氏の間に崇仏論争があり、敏達天皇の廃仏令によって仏舎が焼かれ仏像は海に捨てられた。すると天皇と物部守屋はたちまち瘡を患い、また国中に瘡を発して死ぬものが満ちあふれた、とある。光明皇后は、膨大な数の死亡者が発生したのは個々の人間の罪の報いではなく、国家そのものの罪の報いと感じたのではないか。解決は国家・天皇が深く懺悔し、仏教を大々的に擁護するしかない、という結論になる。取り組みが遅れれば人々の不安や不満はつのる。それが「天災は天皇の失政が原因」という藤原広嗣の乱の口実に利用された。政権が倒される可能性もある。これが唐突な国分寺建立の詔になったと思う。
最後に金光明最勝王経を天皇に勧めた道慈について
天平時代に活躍した僧侶に道慈と玄昉がいる。玄昉は高校の日本史の教科書に載っているので有名だが(光明皇后に重用され、そのため藤原仲麻呂ににらまれて一時九州に左遷されるなど政治に関係したため。)先輩の道慈はほとんど知られていない。道慈は702年の遣唐使で留学僧として唐に渡り718年に帰国。滞在中に義浄(有名な玄奘三蔵法師がインドに渡ったようにやや遅れて海路を伝ってインドに渡った僧。)がインドから持ち帰った金光明最勝王経を翻訳したのである。出来上がったばかりのこの経を現地で学び、帰国した後は聖武天皇の顧問になった。玄昉は717年の遣唐使に従って入唐し、734年に帰国。同じく政治顧問となる。彼が中国の安国寺で行われた尼僧の滅罪活動を伝えたという。国分寺建立の詔の文章が玄昉の文体に似ているため彼が起草したと考える人もいる。もしそうなら、「やっぱり国分寺、国分尼寺の設立推進者は実は光明皇后だったといえるのだが。これは我田引水か。 おわり
私は仏教の専門家でもなく、お経をしっかり読んだわけでもありません。手近にある書物を調べ、考えてみました。間違いがあれば教えてください。