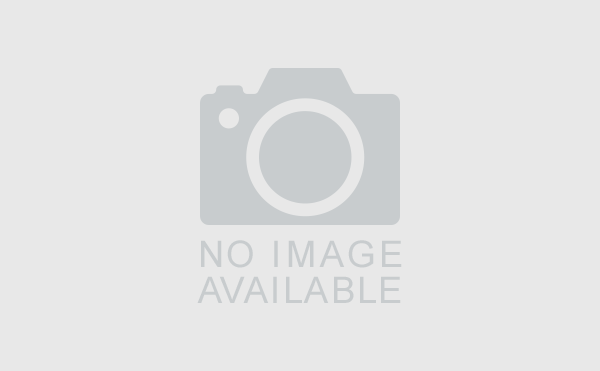国分尼寺と法華経
新・三河国分尼寺史跡公園ボランティアガイド日記・6 2025年3月16日 三浦茂
国分尼寺は「法華滅罪之寺」というのが正式名称で法華経を読むことで疫病の原因の罪を滅すのが目的だったと考えられる。全国の総国分寺が東大寺で総国分尼寺が法華寺である。今回は尼寺と不可分な法華経についてまとめてみた。
日本最初の仏典解説書の三経義疏は聖徳太子が書いたとされるが、法華経、勝鬘経、維摩経の三経を選んだ聖徳太子の仏教理解の深さに感心した。(本当は渡来僧の指導があったろうが。)法華経は出家僧だけでなく、すべての人が成仏できることを説き、勝鬘経は在家の女性、維摩経は在家男性信者の成仏を説いているからである。それなのに古代仏教はなぜ女性の成仏はない。という考えが支配的だったのか。坊主どもはお経を読みながら、ちっとも内容について理解していなかったのか。不思議である。
法華経の提婆達多品に龍女成仏の話が載っており、これが女性も成仏できる根拠にされた。という説がかつてあった。経典には龍女に智積菩薩と舎利弗が、「釈迦でも大変な修業を要した。人間でもない龍(畜生)であり、しかも女であるから成仏はできない。」と言ったことが載っている。仏のように立派な菩薩や釈迦の弟子の舎利弗のような人ですらこう考えるのが当時普通だったのだろう。「女性で仏陀になったものはいない。」と言われたのに対し、龍女はたちまち男に変身し、成仏した姿を現して大衆に説法した。大衆は歓喜し、二人は黙ってしまった。とある。印象的な話ではあるが、研究者によればこの章(提婆達多品)はサンスクリットの原本にはなく、どこかで紛れ込んで中国に伝わったとされる。この話だけでは龍女だからできた特別な事例ではないかと考えてしまうが、この章が特別なのである。聖徳太子が選んだだけあり、法華経は他の章でもちゃんと女性が成仏できることを説いている。
第一章(序品) 釈迦が法華経の説法をされるとき千二百人の弟子のほか釈迦の養母とかつての王妃を含め何千人もの女性出家者、八万人の菩薩、無数の神々などあらゆる階層のものが集まった。ここに集まった女性たちはこのあと成仏を約束された。
第八章で十大弟子の一人フルナに授記(未来の成仏を予告)したとき、与えられる仏国土に悪は無く女もいない。とあり、悪と女性を排除している。このような記述は他になく、この箇所は後世の付加であるという意見(刈谷定彦)がある。その証拠に舎利弗の予告された仏国土には女性が充満している。という記述がある。浄土教の「極楽浄土には女性は一人もいない。(無量壽経)とする思想が後世に盛り込まれた可能性がある。
第十二章で釈迦滅後の弘教について話している時に唐突に二人の女性が、私たちはまだ授記されていない。と申し出る。釈迦はあなた方を含めてすべての聴衆に授記した。という。しかし女性が本当に成仏できるのか、という不安から名前を呼んで授記してほしい、という2人の気持ちを察して釈迦はもう一度授記した。2人の付き人四千人と六千人も授記された。唐突なエピソードの挿入は、女性は成仏出来ない。という当時の常識に、「そんなことはない‼」と強調する効果を狙ったようにみえる。この経を広める者は身の危険もあると法華経に書いてあるほど社会の壁は厚かったようだ。
古代国家はどこでも階級社会だったが特にインドは侵入したアーリア人が先住民を支配した上にアーリア人の内部にも宗教に裏打ちされた厳しい身分制度があった。統一国家形成前の戦国時代の社会混乱の中で生まれた仏教は人々の日々の生活の中にある苦痛と迷信的社会的拘束からの解放を目指すものだった。釈迦は人々の苦しみに寄り添い、苦痛の原因を分析し、苦痛を乗り越える一つの方法を提示した。また迷信的で聖職者しか救われないという古来のバラモン教を否定し、すべての人が救われる。という革命的思想を打ち出した。前者は精神分析と行動療法にあたる近代的処方で、私は釈迦が宗教家というより優れた精神カウンセラーであったと考える。後者は伝統的神(インド社会に深く根差した思想、文化、生活様式)に対し、針で象に立ち向かうような挑戦だったと思う。哲学も政治学もなかったの時代の人はこの思想を宗教として捉えたかもしれない。外出ができない雨季に使う竹林精舎は寺の始まりだが、病んだ心のリハビリ施設の役割を果たしたかもしれない。
一部の人が釈迦の考えを受け入れたが、この団体は長らく社会の少数派だった。圧倒的な旧思想の圧力のなかで継承者(弟子)たちはいつの間にか思想面でバラモン教の保守的な考え方と融合し、反対派との対抗上釈迦を神格化し、同時に自分たちを特別な地位にあるものとする教義を作り上げた。それを部派仏教、あるいは小乗仏教と呼ぶ。
原始仏教(初期仏教)のパーリ語経典では出家、在家、男女の別なく覚りをえることができる。「私は人間である。」という釈迦の言葉が載っている。覚り方は「即身成仏」一瞬にして覚りを得る。「一生成仏」生まれ変わらなくても覚りを得る。とされた。
*(覚り(さとり)とは真理に目覚めること。目覚めた人は覚者(ブッダ=仏陀)。
小乗仏教では
仏陀になれるのは釈迦だけ。(天文学的修行期間がいる。)出家(男性)は修行でアラハン(仏に次ぐ位)にまでなれる。在家はアラハンに至れない。女性は全く成仏できない。
その他 信徒に布施を要求、戒律を変えて僧団(代理人)が金貸しをすることを認めた。
こんな状態では宗教改革運動が起こります。改革派の大乗仏教にも各派があり、小乗派と対立。大乗派の中で小乗派や迷信を信じる多くの庶民も取り込んでいこう、という考えで編まれたのが法華経です。(小乗も否定せず、現世利益を求める民間思想も混在)
最後に金光明経について。他の経と比べるとずいぶん遅れて4世紀ころインドで成立。内容は空の大乗思想を基調。まず経典を護持する功徳を説く。次いで本論、
妙幢菩薩が永遠の寿命の釈迦が80歳で涅槃に入った疑問を呈す。如来は常住なる法身で涅槃は方便であるあるとされ納得。また夢に金色に輝く鼓が現れ懺悔の偈(箴言、歌)を出す。その後空性説も説かれる。目覚めた後釈迦の元に行き夢の意味を教えてもらう。(金色の鼓が経典の名前の由来。そして「懺悔」がこの経の主テーマ)
仏教を含めインドの世界観では人の行為は業であり、良い業も悪い業も生まれ変わった世界で報いを受ける。その世界での行為は次の業として次の報いを生む。業と報いは絶対切り離せないもので人は輪廻を繰り返すというものである。大乗仏教は如来の慈悲によって輪廻の法則から人を解放しようとした。懺悔と回向によって業報の法則を超越できるというものだ。本文の後に非常に長い流通本(後書き)があり、そこに四天王などの神々が経を護持する国王国土を守る、と説いている。そのほかに様々な経の功徳などが書いてある。私見ながら流通本は別の経典が付け加えられたようにみえる。初期の編纂時だろう。西域地方に伝わった時には四天王崇拝が起こり、中国では金光明懺悔法が流行した。日本に伝わったのは早かったが、聖武天皇が重視したのは、インドから最新版を持ち得った義浄が則天武后の勅命で漢訳したての金光明最勝王経が手に入ったのでストレプトマイシンのような特効薬と感じたのではないかと想像する。